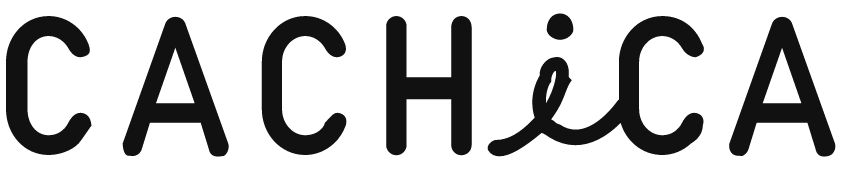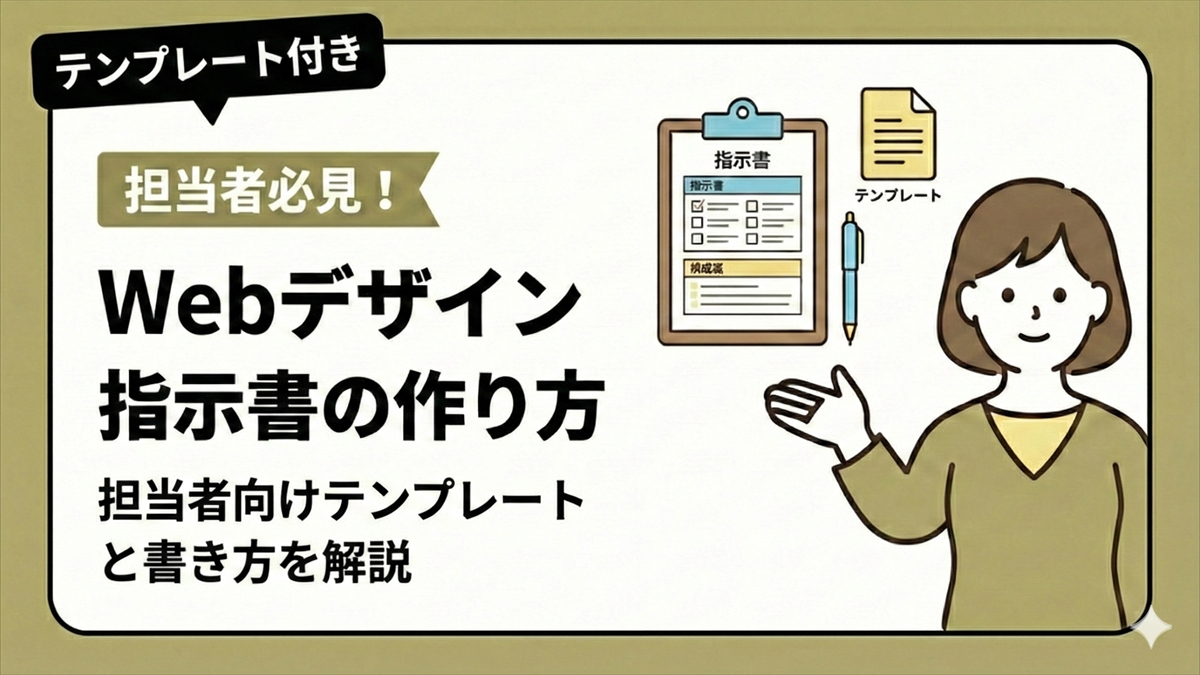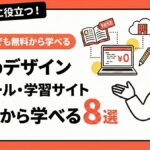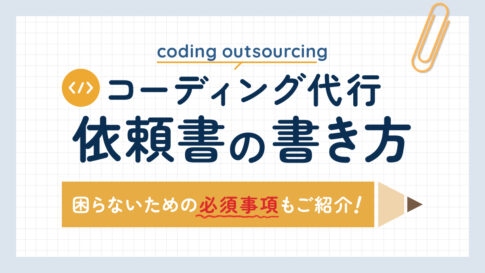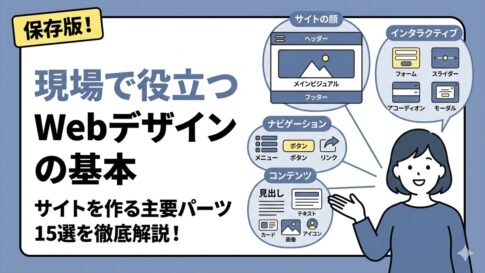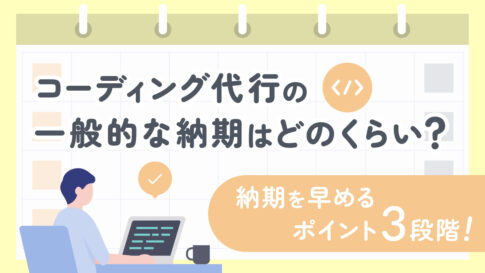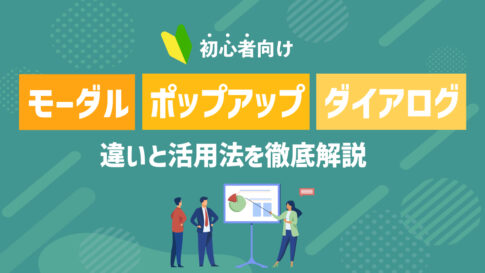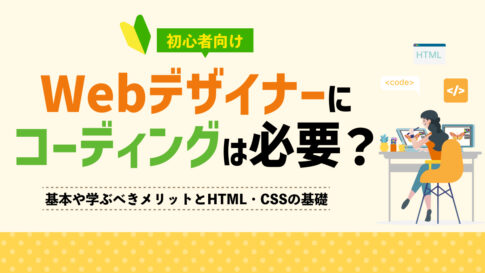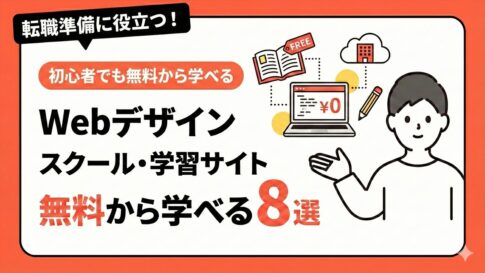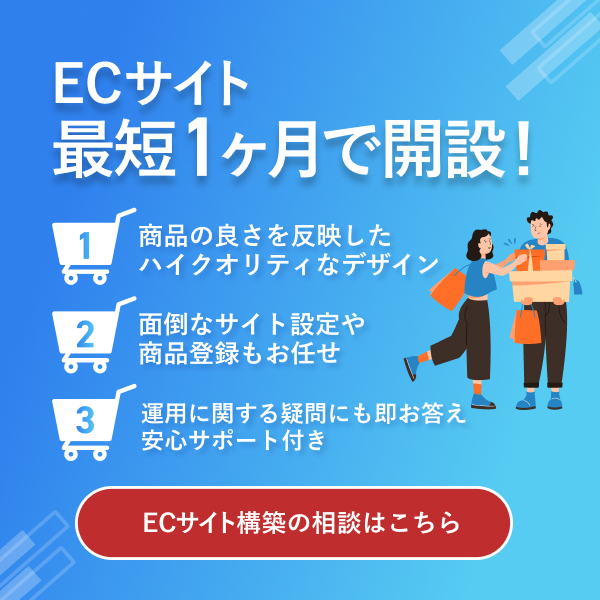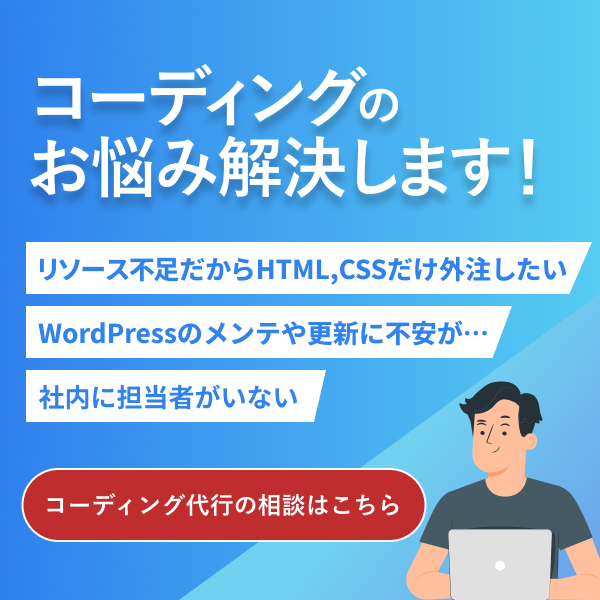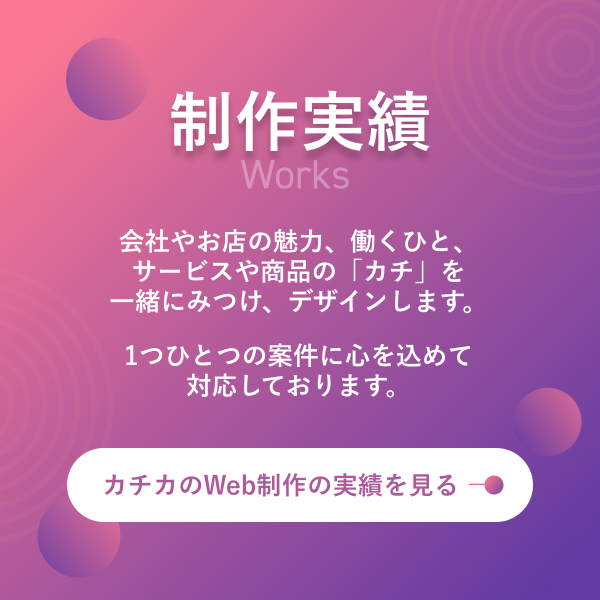「思っていたデザインと違う…」「修正が多すぎて納期が遅れる…」
Webサイト制作でこんな悩みを抱えたことはありませんか?
その多くは、外注先や社内チームへの依頼時に作成する“Webデザイン指示書”の準備不足が原因です。
指示書は単なるチェックリストではなく、プロジェクト全体を導く設計図の役割を持っています。
しっかりとした指示書を用意すれば、制作の方向性を共有でき、無駄な修正やコスト増を防ぐことが可能。
この記事では、担当者の方がすぐに活用できるWebデザイン指示書のテンプレートと作成ポイントを解説します。
外注依頼を控えている方や社内ディレクターとして動く方にとって、担当者と制作者の認識齟齬を減らすための、実践的なヒントになるでしょう。
Webデザイン指示書とは?必要な理由
Webデザイン指示書とは、制作プロジェクトを成功に導くための設計図。
指示書を作らない、あるいは曖昧なまま進めてしまうと、次のような問題が起こります。
- デザイナーに意図が伝わらず、修正回数が増える
- 依頼者と制作者で「完成イメージ」がずれてしまう
- 結果として納期遅延や追加コスト発生のリスク大
指示書は「担当者→制作者」の一方通行の文書ではなく、共通言語としての役割を果たします。
依頼者、デザイナー、ディレクターが同じ目標を共有することで、制作の効率と完成度が飛躍的に高まります。
【基本項目】必ず入れるべき内容
プロジェクト概要
最初に整理すべきは、プロジェクトの基本情報。
特に「制作の目的」と「ターゲット層」の明記は欠かせません。
これらが曖昧なままでは、デザインの方向性や訴求する相手がぶれやすく、完成後に大きな齟齬が生まれてしまいます。
指示書の土台として、必ず最初に丁寧に言語化しておくことが重要です。
| 項目 | 内容説明 | 記入例(サンプル) |
|---|---|---|
| プロジェクト名 | 一目でわかる名称 | 株式会社〇〇 コーポレートサイト |
| 制作目的 | なぜこのサイトを作るのか? | ・問い合わせ件数の増加 ・採用ページ強化 |
| ターゲット層 | 誰に見てほしいのか? | ・20代女性 ・経営者層 ・子育て世代の親 |
| 公開予定日 | 納期を明確化 | 2025年12月1日 |
デザインの方向性
デザイナーが作業の途中で迷わないようにするためには、サイトの見た目の雰囲気や色使いをできるだけ具体的に記載することが大切。
抽象的な表現では解釈が分かれてしまうため、方向性のずれにつながります。
◎:「シンプルで信頼感のあるデザイン」 ✕:「かっこいい感じ」
| 項目 | 内容説明 | 記入例(サンプル) |
|---|---|---|
| サイトの雰囲気 | どのような印象を与えたいか | ・信頼感 ・親しみやすさ ・高級感 など |
| キーカラー/テーマカラー | ブランドを象徴する色 | ・青(信頼感) ・緑(自然・安心) ・黒(金属的・高級感) |
| 参考サイトURL | 好きなデザインや方向性の例を提示 | ・URLを記載(配色が好み) |
| NGデザイン | 避けたい雰囲気や例を具体的に記載 | 「派手すぎる色使い」 「過度なアニメーション」 |
ページごとの構成
ページごとの構成が曖昧なまま進めてしまうと、「ここは載せると思っていた」「この情報は不要だった」といった齟齬が必ず発生します。
その結果、修正依頼が増え、納期やコストに大きな影響を及ぼす原因に。
だからこそ、最初の段階で構成を具体的に整理しておくことが欠かせません。
| 項目 | 内容説明 | 記入例(サンプル) |
|---|---|---|
| ページリスト | 制作するページの一覧 | ・トップ ・会社概要 ・サービス一覧 ・お問い合わせ |
| コンテンツ内容 | 各ページに掲載するテキスト・見出し・画像の指示 | ・トップページ:メインビジュアル ・サービス紹介 ・CTAボタン |
| レイアウト指示 | ページの構成イメージ。簡単なワイヤーフレーム(手書き可)を添付 | トップページ上部に大きな画像、その下にサービス3つを横並びで配置 |
素材とその他
最後にまとめるべきは、制作に必要となる各種データや連絡体制。
ロゴや写真素材、文章の準備状況、担当者の連絡先などが明確でないと、制作は必ず途中で止まってしまいます。
どんなにデザインや構成が整っていても、素材や窓口情報が欠けていると進行が滞り、納期やコストに直結するリスクも。
だからこそ、仕上げの段階でこれらを丁寧に整理し、抜け漏れのない状態で共有することが重要です。
| 項目 | 内容説明 | 記入例(サンプル) |
|---|---|---|
| ロゴデータ | 使用するロゴの有無やデータ形式 | ・あり(AI/PNG形式) ・なし(新規作成依頼) |
| 写真・テキスト | 各ページに掲載する素材を依頼者が用意するか、制作会社に依頼するか | ・写真:依頼者提供 ・文章:制作会社に依頼 |
| 担当者情報 | 制作中の窓口となる担当者名と連絡先 | 山田太郎(marketing@example.com) |
【コピペOK】Webデザイン指示書テンプレート
以下のテンプレートをコピーし、表内を埋めていくだけで完成させられます。
基本情報
まずはプロジェクト全体の基本情報を整理することから始めましょう。
ここをしっかりまとめておけば、制作チーム全員が同じ方向を見て進めることができます。
情報が明確に共有されるほど、サイトの目的やゴールも自然とブレずに実現できます。
| 項目 | 内容説明 | 記入例(サンプル) |
|---|---|---|
| プロジェクト名 | サイトを識別できる名称 | 株式会社〇〇 コーポレートサイトリニューアル |
| 制作目的 | サイト制作のゴール・目的 | ・信頼性を高める ・お問い合わせ件数を増やす |
| ターゲット | 想定するユーザー層 | ・30〜40代 IT企業担当者 ・20代女性 ・経営者層 |
| 公開予定日 | 納期・公開スケジュール | 2025年12月1日 |
デザインの方向性
次に取り組むのは、デザインの方向性をしっかりと明確にすること。
この部分があいまいだと、完成後に「思っていたイメージと違う」といった大きな齟齬が起きやすくなります。
見た目の雰囲気や色使いを具体的に記載しておくことで、制作途中のトラブルを未然に防ぎ、安心してプロジェクトを進められるようになります。
| 項目 | 内容説明 | 記入例(サンプル) |
|---|---|---|
| サイトの雰囲気 | 与えたい印象・トーン | ・信頼感のある ・親しみやすい ・スタイリッシュ |
| メインカラー/テーマカラー | ブランドや目的に合わせた色 | ・青(信頼) ・緑(安心感) ・黒(高級感) |
| 参考サイトURL | 好きなデザイン例と理由 | ・URLを記載(配色が好み)(動きが洗練されている) |
| NGデザイン | 避けたいデザインの方向性 | ・派手すぎる色 ・過度なアニメーション ・ごちゃごちゃした配置 |
ページ構成
続いて取り組むべきは、ページごとの構成と掲載内容をしっかりと整理すること。
どのページに何を載せるのかが曖昧なままだと、制作の途中で「ここは必要だった」「この情報は不要だった」といった齟齬が必ず発生するでしょう。
その結果、修正依頼が増えて余計な工数がかかり、納期の遅れやコストの増加につながる危険性があります。
だからこそ、最初の段階でページ構成を具体的にまとめておくことが、スムーズな進行と完成度向上になります。
| 項目 | 内容説明 | 記入例(サンプル) |
|---|---|---|
| ページリスト | 制作予定のページ一覧 | ・トップ ・会社概要 ・サービス一覧 ・お問い合わせ |
| コンテンツ内容 | 各ページに掲載する情報 | ・トップ:メインビジュアル ・サービス紹介 ・CTAボタン |
| レイアウト指示 | 配置イメージやワイヤーフレーム(手書きでもOK) | ・上部:メイン画像 ・中段:サービス3つを横並び ・下部:問い合わせ導線 |
素材や担当者情報
最後に欠かせないのが、制作に必要となる素材や担当者情報を明確にしておくこと。
ロゴデータや写真、文章の準備状況、そして窓口となる担当者の連絡先が整理されていないと、制作は簡単にストップしてしまいます。
あらかじめ抜け漏れのない状態で共有しておけば、安心してスムーズに進行でき、納期や品質の安定にもつながります。
| 項目 | 内容説明 | 記入例(サンプル) |
|---|---|---|
| ロゴデータ | 使用するロゴの有無・形式 | ・あり(AI/PNG形式) ・なし(新規作成依頼) |
| 写真・文章 | コンテンツ素材の準備状況 | ・写真:依頼者提供 ・文章:制作会社に依頼 |
| その他素材 | バナー・アイコンなど | ・既存素材あり ・新規作成希望 |
| 担当者情報 | 制作中の窓口となる人と連絡先 | 山田太郎(marketing@example.com) |
指示書作成のポイントと注意点
曖昧な表現を避ける
抽象的で漠然とした表現は、依頼者にとっては自然でも、デザイナーには解釈の幅が広すぎて正確に伝わりません。
例えば「おしゃれ」や「かっこいい」といった一言だけでは、人によってイメージが異なり、仕上がりに大きな差が出てしまいます。
そのため、できるだけ具体的な言葉で意図を伝えることが重要です。
表のように、色や要素、雰囲気を具体的に言語化することで、デザイナーとの認識のずれを最小限に抑えましょう。
結果として修正回数の削減につながり、スケジュールやコストの面でも大きなメリットを得られます。
| NG表現 | 改善後の具体的な指示 |
|---|---|
| 「おしゃれ」 | 親しみやすいイラストを使って温かい雰囲気に |
| 「かっこいい」 | 青を基調に落ち着いた印象を与えるデザインに |
| 「明るく」 | 白と黄色を中心に使い、清潔感と爽やかさを演出 |
ワイヤーフレームを添える
文章だけで指示を伝えようとすると、どうしても解釈の違いが生まれやすく、誤解の原因になります。
そのため、シンプルであっても図を添える工夫が効果的。
ワイヤーフレームは特別なソフトを使わなくても構いませんし、手書きのスケッチで十分役割を果たします。
重要なのは、ページ全体のレイアウトや構成の大枠を図示して共有すること。
こうした視覚的な補足があるだけで、デザイナーの理解度が大きく高まり、意図が正確に伝わります。
ワイヤーフレームがあるかないかで、修正工数や作業効率には大きな差が生まれます。
「なぜ?」を伝える
「なぜこの色を選んだのか」「なぜこの要素を入れるのか」といった背景を伝えることは、デザインの意図を正しく理解してもらうために欠かせません。
単に指示を出すだけではなく、目的や理由を共有することで、デザイナーはより的確で質の高い提案を行えるようになります。
こうした意図の共有は、依頼者と制作者の間に信頼関係を築き、結果としてプロジェクト全体の完成度を大きく高めることができるでしょう。
| 項目 | 伝える内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 色の選定理由 | 「青=信頼感を表現したい」など、背景を説明する | デザイナーが狙いを理解し、適切な色合いを提案できる |
| 要素の意図 | 「CTAを目立たせて問い合わせを増やしたい」など | 配置や強調の工夫が反映され、目的達成に近づく |
| 背景や目的 | サイトのゴールや依頼者の意図 | 制作側の提案力が高まり、齟齬が減る |
まとめ
ポイントまとめ
ポイントまとめ
・Webデザイン指示書はプロジェクトの設計図。
・曖昧な依頼は修正の連鎖を招く。
・プロジェクト概要、デザイン方向性、ページ構成、素材情報の4点を必ず明記する。
・ワイヤーフレームの提示と「なぜ?」の共有が成功の分かれ目になる。
限られた時間や予算の中でも、指示書を最適化することでプロジェクトは大きく変わります。
本記事は、目的に合った“伝わる指示書”を作るための第一歩としてご活用いただけます。
テンプレートは誰でもコピー可能ですので、ぜひ役立ててください。