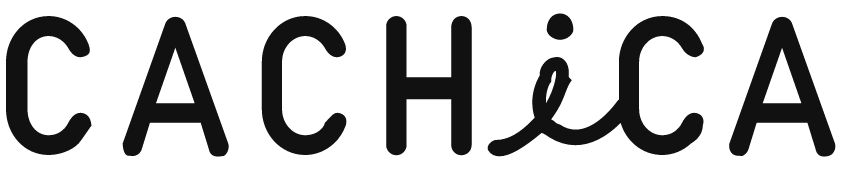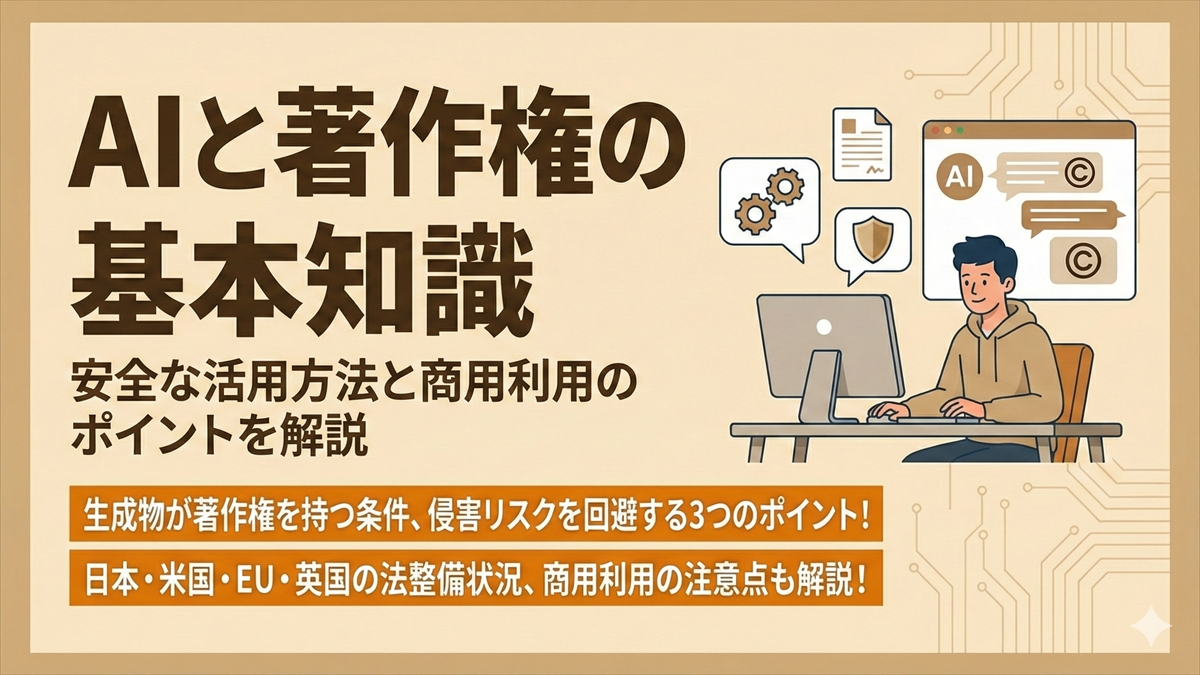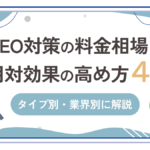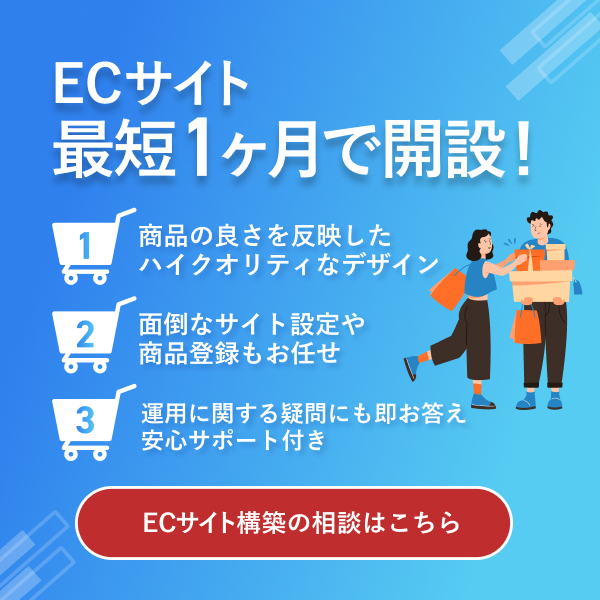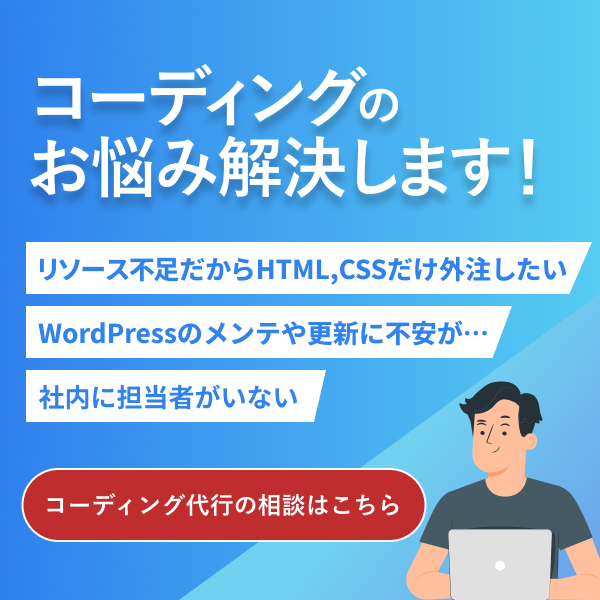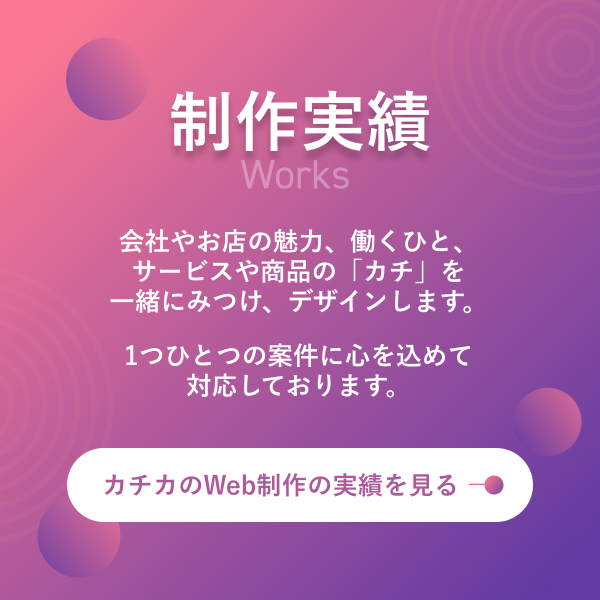生成AIの活用は私達の生活や、企業活動に欠かせない存在となりつつあります。
家庭では宿題やレポート作成、企業では資料作成や企画、画像生成まで幅広く使える一方で、「著作権」の不安を耳にすることも多いでしょう。
法的な整備はまだ途上にありますが、だからこそ現状のルールを正しく理解することが大切です。
本記事では、個人や家庭における使用から商用利用において、安心して生成AIを使いこなすための基本的な考え方を紹介します。
生成AIと著作権の関係を十分に理解して、AIが秘めるポテンシャルを安全に、より効率的に業務に、生活に活用していきましょう。
目次
生成AIが作ったものに著作権はあるのか?
多くの人が気にする、AIが生成した画像や文章の著作権は、一体どうなるのでしょうか。
結論から言えば、日本においては「著作権は原則として『人間の創作的表現』に付与される」としているため、生成AI単体が作ったものに権利は発生しません。
ただし、次にような場合は著作権が認められる可能性があります。
- プロンプト(生成指示文)に創作者の相応な工夫が見られる
- AIが生成した後に人間が編集や加工を加えた
- 人間の創意工夫が明確に現れている
つまり、AIを道具として用いるだけでなく、「人間が創造的な関与をしていること」がポイントです。
各国のAI著作権法の整備状況
AI著作権の二種類の問題
AIに関する著作権では大別して次の二種類の問題が存在します。
- AIが生成した画像や文章に著作権を認めるか
- AIが膨大な著作物を取り込む学習により実現する、「機能」や「生成物」を商用利用することが著作権法に抵触しないのか
現在、法的に確立しておらず、各国で法制化の検討・審議が行われている最中です。
以下に日本、英国、EU、米国の状況を比較できるよう纏めました。
この内容は、2025年9月時点のものであり、今後の議論による変更が予想されることに留意して下さい。
日本
日本では、従来の著作権法の枠組みを堅持しつつ、その枠内での解釈・運用の整備を進めています。
| AI生成物に著作権が認められるか | 原則として認められない(人の創作性が必要) |
| 著作権主体 | 著作権は人間の「思想・感情の創作的表現」が対象である |
| 備考 | AIは著作者になれないが、人がプロンプト等で創作的関与をすれば著作権が認められる可能性あり |
| 商用利用時の視点 | AI単独生成物は著作権が無く、模倣や盗用の権利侵害が成立しない場合がある |
| リスク | 著作権が認められない作品は「誰でも利用可能」となり、模倣品やブランド毀損リスクが高い |
| リスクの回避策 | 人間の創造性により著作権が認められる著作物を用いる契約や利用規約で利用ルールを明示する/学習データ由来の権利侵害リスクに注意 |
英国
画像生成ツールの開発・運営企業と報道・広告画像の供給元企業の間でAI学習データの無断使用に関する訴訟が続いている。
一方、英最高裁判所は、発明者をAIとする特許を認める訴訟を棄却した。
しかし、そのプロンプト(AIに対する命令文)の入力者を発明者とした場合は特許を認める可能性を推測させる内容が報じられている。
| AI生成物に著作権が認められるか | 条件付きで認められる可能性あり(特殊規定あり) |
| 著作権主体 | 「当該生成に必要な手配を行った者」が著作者とされる 手配を行った者とは、プロンプト入力者だけでなく、開発者、運営者が含まれる可能性がある |
| 備考 | 世界的にも珍しい規定だが、AI時代全般に適用できるかは議論中 |
| 商用利用時の視点 | AI生成を「手配した者」が著作者とされる可能性あり(上記) |
| リスク | 当該法規は実務上ほとんど使われておらず、AI作品にどこまで適用されるか不透明実務では「契約」「利用規約」「商標」などの法制度に依存する傾向が強い |
| リスクの回避策 | AI生成物に保護が及ぶ可能性はあるが過信は禁物社内規程で生成AIの利用・帰属をルール化しておく |
EU
2026年8月からEU AI規制法が適用される予定です。
この法律では、
- 「AI生成」ラベルによるユーザーに対する生成起源の明確化
- AIの学習に用いるデータが著作権法(EU著作権指令など)への準拠
- ディープフェイクの重点的規制
などが強化される見込みです。
EUでは、狭い著作権の範疇ではなく、AIが社会に与えるリスク全般を対象に議論しています。
新たな「AI規制法」により、AI利用と社会秩序のバランスを図る施策を目指しています。
| AI生成物に著作権が認められるか | 原則として認められない(人間の創作性が前提) |
| 著作権主体 | 欧州司法裁判所は「著作権は人間の知的創作に限る」と解釈 |
| 備考 | 欧州委員会・議会ではAI著作権を含めた包括的制度設計を議論中 |
| 商用利用時の視点 | 原則「人の創作性」がないと著作権保護なしAI法で透明性やデータ利用規制が強化される |
| リスク | 無断で学習に使われたデータ由来の権利侵害や、消費者保護上の責任追及リスクあり |
| リスクの回避策 | 著作権保護に依存せず、契約・商標・ブランド戦略を強化する生成過程の透明性を担保する |
米国
日本や英国、EUと同じく、AIが人間の関与を得ずに作成したコンテンツには著作権を認めないという点では共通しています。
米国著作権局が提示した「プロンプトのみによる生成物は著作権保護を認めない」という判断は日本や英国、EUと大きく異なり注目に値します。
| AI生成物に著作権が認められるか | 原則として認められない(人間の関与が ”必須”) |
| 著作権主体 | 「人間の著作者」に限られる |
| 備考 | 人間の創造的な選択・編集が加われば、その部分は保護対象になり得る |
| 商用利用時の視点 | 著作権局は「人間の関与がないAI生成物」に著作権を認めない関与部分の保護は可能 |
| リスク | 作品著作権登録が拒絶される可能性大 |
| リスクの回避策 | 人間の関与を明確に記録(プロンプト内容・編集工程)/作品登録は人の寄与部分を強調する商標・契約を主体に保護を検討 |
海外を対象とする商用利用で留意すべき点
企業、個人を問わず、海外を対象にして生成AIを商用利用する場合には、AIに関する現地の法解釈が日本国内と異なることを前提にすべきです。
- 対象国のAI著作権法とその整備状況を逐一確認
- 商取引契約におけるAI生成物の権利帰属の明確化
これにより、生成AIを商用利用する際の安全性を高めることができます。
生成AIが学ぶデータと著作権の関係
生成AIは既存の何十億、何百億という膨大な画像や文章などをデータとして蓄積、学習して、そこから新たなコンテンツを生成します。
日本の著作権法では、「情報解析の用に供する場合」に限り、著作権者の許可なく著作物を利用できると定められています。
しかし、これはあくまでも研究や教育の範囲における「非営利目的」での利用や、「著作権者の利益を不当に害しない」という条件の下でのこと。
他者の作品を含むデータで学習したAIの生成物をそのまま商用利用すると、状況によっては権利侵害とみなされるリスクがあります。
生成AIの学習に関する文化庁のガイドラインでは、「グレーゾーンが多くケース・バイ・ケース」としつつ、無断使用は慎重に扱うべきとの立場です。
つまり、現行法では、AI学習に著作物を無断で使用することはリスクを伴うということです。
日本国内に限らず、米国、英国、EUなどの諸外国でも、AI著作権の関連法規は整備、模索が続いている状況です。
国内、海外における、今後の法解釈や議論の動向を継続的に注視する必要があります。
AI著作権トラブルを防ぐ3つのポイント
生成AIの著作権をめぐるトラブルを避けるために、以下の3点に注意しましょう。
1.利用規約を確認する
AIツールごとに、商用利用が可能か、生成物の著作権がどうなるかといったルールが定められています。
まずは、必ず公式の利用規約を確認しましょう。
利用規約は改定されることもあるため、ユーザー登録により利用規約の改定通知を入手可能しておくと安心です。
2.生成物の意図しない類似に注意する
AIで生成した文章や画像は、学習過程でデータとして読み込んだ著作物の影響を受けることがあり得ます。
このために、意図せず元データの著作物に類似した表現や構図が生成される可能性が排除できません。
商用利用や外部公開の前には必ず生成物を確認し、類似の有無をチェックするようにしてください。
特に、有名なキャラクターや特定の画風に似た画像、ブランドロゴ近似品を生成しないように気を配りましょう。
そのためには、生成物の検証フローや修正・独自化の手順を確立しておくと、著作権に抵触するリスクやトラブルの防止に役立ちます。
3.AI生成作品の出所を明らかにするための「クレジット」を明記する
「クレジット」とは、その生成物の出典元や著作者を示すものです。
AIツールの利用規約で要求されている場合を除き、多くのAIツールでは生成物にクレジットを明記することを求めていません。
しかし、透明性の確保、倫理、コンプライアンス対応などからは自主的なクレジット表記を検討しましょう。
ツールによっては任意で表記する場合の(推奨)文言を提示している場合もあります。
自作品の著作権登録は不要!
結論から申し上げますと、自分の作品の著作権を登録する必要はありません。
それは、なぜか?
また、偽作や盗作に対して著作権侵害を訴えるにはどうすれば良いのでしょう?
ここでは、自分の諸作物の権利を護る手段を考えていきます。
著作権は自動的に発生
特許権や商標権とは異なり、著作物を創作した時点で著作権が自動的に発生します。
そのため、原則として、著作権を主張するための申請や登録は必要ありません。
※著作権には「著作権登録制度」がありますが、制度を利用する費用と時間を使わずとも、作品創作時のエビデンス類を整理・保管することで対応が可能です。
著作権の主張にはエビデンスが必要
「著作権登録制度」を利用する、しないに拘らず、「その作品を自分が創作した」という主張にはエビデンスが大きな効力を発揮します。
「どんな条件で、どのようにして、その作品が生成されたか」を後から再現・説明できる情報の一式(プロンプト、シード、生成日時、出力ファイル、編集履歴)が、最も重要なエビデンスです。
以下に主要な内容を列挙します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生成プロセス関連 | 使用した プロンプト(入力指示文) |
| ネガティブプロンプト(除外指示文) | |
| 生成モデル名・バージョン(例:Stable Diffusion 1.5 / DALL·E 3) | |
| 生成日時(自動記録 or 手記メモ) | |
| シード値(乱数種)(再現可能性の証明に有効) | |
| 出力ファイル関連 | 生成されたファイルそのもの(画像・文章・音声など) |
| ファイルのメタデータ(作成日・環境情報) | |
| 途中生成物やバリエーション(「失敗作」や複数候補を含む) | |
| 補強資料 | 生成環境のログ(サービス利用履歴、ブラウザ履歴、コマンドログなど) |
| 生成直後のスクリーンショット(生成画面、設定が分かる状態が理想) | |
| 利用アカウントの記録(誰が生成したかを示す) | |
| 編集・加筆履歴 | 編集ソフトのプロジェクトファイル(例:.psd, .ai, .prproj) |
| 加工の段階的ファイル(Before/Afterを残す) | |
| 自分の関与メモ(どこに工夫を加えたか、意図した表現など) |
エビデンスの有効な運用方法の参考例を記しておきます。
- 作品ごとに 「プロジェクトフォルダ」 を作成し、上記の項目をまとめて保管
- クラウドや外付けHDDにもバックアップを保存
まとめ
ポイントまとめ
(AIの安全利用)
・AIツール利用規約の十分な理解と遵守が必要
・利用規約で「クレジット」要求がなくても、自主的なクレジット表記を検討(透明性の確保、倫理、コンプライアンス対応などの観点)
(AI生成物の著作権)
・国際的に「AIの生成物は基本的には著作権を持たない」という考えが主流
・AI生成物の著作権を主張するには、プロンプトの工夫、生成後の加工など、「人間の創作的関与」の証跡が必要
2025年1月米国著作権局は、プロンプトのみによる生成物には著作権保護を認めないという明確な立場を示しました。
この事実は今後、各国がAI著作権法を模索していく上で影響を及ぼす可能性があります。
更に、2026年8月に施行されるEU AI規制法も注目されます。
著作権という狭い視野から「社会秩序のバランスを図る」という理念がどこまで浸透するかに注目しましょう。